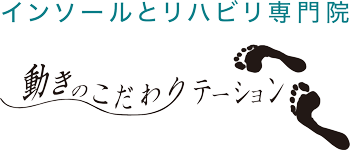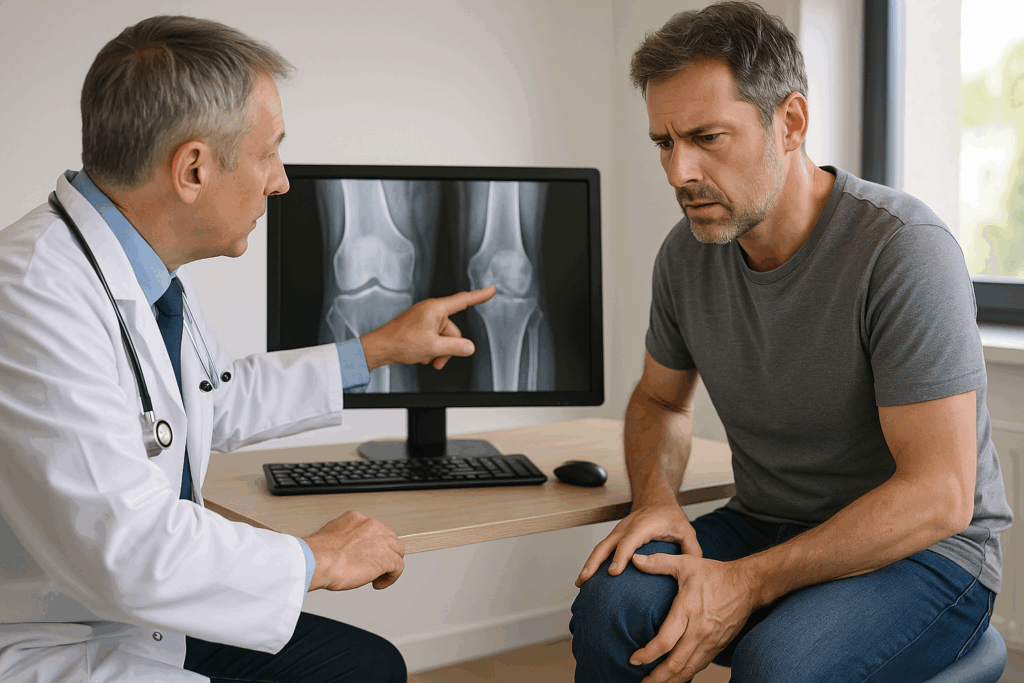
診断名がついたからといって痛みが解決するとは限らない理由
膝が痛くて病院を受診したら、レントゲンを撮って「膝が変形していますね」と言われたことありませんか。
そして痛み止めや筋トレを教わったり、注射をした経験がある方も多いと思います。
でも、ふと冷静に考えたら、実際に痛いのは膝の関節そのものよりも少し離れた部分だったり、「本当に関節の痛みなの?」と思ったことはないでしょうか。
- 「痛いのは太ももの前や横、あるいはスネのあたりなんだけど…」
- 「これ関節が痛いからなの?」
- 「関節が問題なのに筋トレが効く理由は?」
このように 診断された場所(膝の変形)=痛みの場所ではない というケースは少なくありません。
なぜ診断名=痛みではないのか
診断名をつけるためには、体の構造的な異常を見つける必要があります。多くは「変形」です。年齢を重ねれば重ねるほど体の形は変化し、骨も変形します。
これを「構造異常」として診断名がつき、そのうえで医療保険での治療がスタートします。
しかし、変形した場所が必ず痛むわけではありません。
もし変形が痛みの原因なら、年を取った人はみな全ての関節が痛くなるはずですが、実際には右膝だけ、左肩だけ、腰だけ…と痛む場所はバラバラです。
痛みを生む本当の場所
つまり、痛みは必ずしも「変形した部分」からだけ出るのではありません。
たとえば、膝を支える筋肉や靱帯の硬さ・動きの悪さが原因で痛みが出ているケースも多くあります。
そのため、変形があるからといって「そこが痛みの元」とは限らず、実際には太ももやスネの筋肉・腱の周辺、あるいはクッション材である脂肪組織が痛みを出している場合もあります。
痛みの正体を見極めることが第一歩
診断名は体の状態を示す大切な情報です。でも、それだけに頼ってしまうと「痛みの場所」と「診断された場所」のズレに気づけません。
「診断名=痛み」と思い込まずに、どの組織が痛みを出しているのかを見極めることが改善の第一歩になります。
だからこそ、痛みで困ったときは、医師と相談しながらセラピストなど専門家と一緒に原因を探ることが大切です。
まとめ
今回は、「診断名≠痛み」のケースがあることをお伝えしました。
この視点を知っていれば、治療がうまくいかないときに「手術しかない」と諦めるのではなく、「他の原因があるかもしれない」と考え、再度調べたり専門家に相談する行動につながります。
納得のいく治療をして、痛みの解決につながるヒントになれば幸いです。